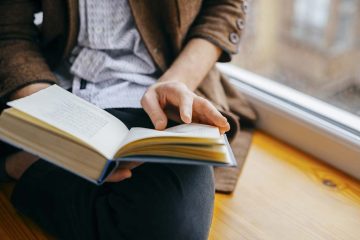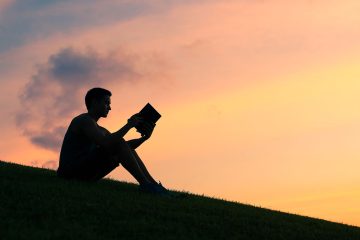先日、小学校の学校公開(授業参観)に行き授業を見てきました。そこでちょっとした気付きを得たため、今日は、約10年後に社会に出てくる子どもたちがどのような教育を受けているのか、彼らが社会に出てきた時にどのようなことに気をつけなければならないかにつき、感じ、考えたことをお伝えします。
授業参観した教科は道徳でした。題材は「泣いた赤鬼」。授業の途中から参加したのでちゃんとストーリーを聞けてはいませんが、赤鬼と青鬼が人間と仲良くなるために、赤鬼が正義の味方となり、悪役の青鬼をやっつけて人間を助けることで、赤鬼が人間と仲良くなるようにしよう、というお話です。
作戦は見事に当たり、赤鬼は人間に感謝をされて友達になれたのですが、青鬼は悪者になってしまい、村を去ります。この物語に対して先生が、赤鬼と青鬼は本当の友達でしょうか、そうじゃないでしょうか、という問いを投げかけます。
今の小学校ではタブレットが導入されていて、意見をタブレット越しに伝えることができます。アンケートの結果、友達だという意見と、友達ではないという意見が分かれたことが一目瞭然で分かりました。
そして、先生が、どうしてそう思うのかを生徒に対して聞きます。生徒は、自分なりの解釈をもとに意見を述べるのですが、それに対して先生が何か意見を言うわけではなく、そういう受け止め方もあるね、そういう捉え方もあるね、といったことを話しておられました。
昔の道徳、それこそ私たちが受けた道徳の授業というのは、こうあるのが正しい、こうあるのが間違っている、といった倫理観をダイレクトに伝える傾向が少なからずあった気がします。今回の道徳の時間は議論が紛糾して時間がなくなってしまい、結局どうこの話を収めたのかが分からないまま終わったのですが、この授業を見て思ったのは、どの意見が正しい、どの意見が間違っている、という話ではなく、いろんな意見があり、それを各々がどう考えるか、受け止めるのかを考える時間のように思えました。
授業参観ののち、大学院の教授による特別講演に参加し、講演終了後に保護者と先生でグループを作って意見交換をしたのですが、同じグループにいた先生の方が仰るには、いま道徳の授業では、正しいことを教えるのではなく、自分でそれをどう捉えるかを教えるようにしているとのことでした。理由としては、昔は大人が信用できるものであったが、いまは大人が信用できない時代になった(正確に言えば、大人が信用できないということが顕在化した時代になった、ということかと思います)からとのこと。大人の言うことが信用できない中でどのように生きていくか。自分が、何をどのように解釈し、判断し、自分の意見や行動を決めていくべきなのか。そういった考えるプロセスを教えるというのが、いまの時代の道徳の時間だそうです。
このような教育を受けてきた世代が社会に出てきたとき、社会人とはこういうものだという話をしても、恐らくうまくはいきません。どうしてこれをやろうとしているのか、その目的は何なのか、それがなぜ意義があるのか、といったことをしっかり説明した上で、相手の疑問に真摯に向きあい共に歩むべき道を作っていく。それはいまでも大事ではあるのですが、この授業を受けた子供たちが社会に出たときに、より一層、意識的にやらなければいけないことだなと思った授業参観でした。